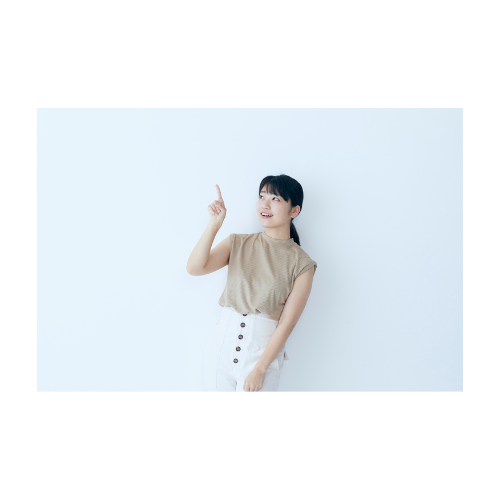Contents
- 岐阜市の解体工事|ご近所トラブルを防ぎ、安心して工事を進めるためには
- 1. はじめに:岐阜市の解体工事、ご近所への配慮は大丈夫?
- 2. 解体工事でよくあるご近所トラブルとは?
- 騒音・振動
- 粉塵・埃
- 作業員のマナー
- 工事車両の駐車・通行
- 隣家への損害
- 境界線・越境物
- 害虫・害獣
- 3. トラブルを未然に防ぐ!解体工事前の準備と対策
- 信頼できる解体業者の選定
- 事前の挨拶回り
- 現場での対策
- 境界線の確認と家屋調査
- 4. もしトラブルが発生してしまったら?冷静な対処法
- 初期対応:聞く姿勢と謝罪
- 情報収集と記録
- 解体業者への迅速な連絡
- 具体的な対応策の例
- 解決が難しい場合
- 5. 岐阜市での解体工事:知っておきたいルールと相談窓口
- 騒音・振動の規制基準
- 作業時間の制限
- 届出義務
- 相談窓口
- 6. まとめ:安心して解体工事を進めるために
岐阜市の解体工事|ご近所トラブルを防ぎ、安心して工事を進めるためには
1. はじめに:岐阜市の解体工事、ご近所への配慮は大丈夫?
こんにちは!岐阜市で解体工事をしているアールサポートです。
岐阜市で建物の解体工事を計画されている方にとって、工事そのものの段取りや費用はもちろんのこと、「ご近所との関係は大丈夫だろうか?」という心配は、大きな関心事ではないでしょうか。長年住み慣れた家や、相続した実家などを解体する際には、様々な思いがあるものです。しかし同時に、解体工事はどうしても騒音や振動、粉塵などを伴うため、近隣住民の方々への影響が避けられません
「工事の音がうるさくて迷惑をかけてしまうのでは…」「粉塵で洗濯物やお車を汚してしまったら…」「もし何か問題が起きたら、どう対応すればいいのだろう…」といった不安を感じるのは、ごく自然なことです
当ブログでは、岐阜市で解体工事を行う際に、近隣トラブルをできる限り避け、皆が気持ちよく工事期間を過ごせるように、知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。「岐阜市」「解体工事」「近隣トラブル」というキーワードに関心のある方々に向けて、よくあるトラブルの事例から、それを未然に防ぐための具体的な対策、そして万が一トラブルが発生した場合の冷静な対処法まで、順を追ってご紹介します。
事前にしっかりと知識を身につけ、適切な準備を行うことで、近隣トラブルのリスクは大幅に減らすことができます。また、信頼できる専門業者と協力し、丁寧なコミュニケーションを心がけることが、安心して工事を進めるための鍵となります。この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、円滑な解体工事の実現に向けた一助となれば幸いです。
2. 解体工事でよくあるご近所トラブルとは?
解体工事には、どうしても騒音や粉塵といった影響が伴います
騒音・振動
解体工事において、最も頻繁に聞かれる懸念事項が騒音と振動です。建物を壊すためには、重機(パワーショベルなど)を使用したり、コンクリートの基礎部分を破壊したりする必要があり、その過程で大きな音や揺れが発生します
法律(騒音規制法や振動規制法)では、作業で出してよい音や振動の上限、作業可能な時間帯などが定められています
粉塵・埃
建物を壊す際には、大量の粉塵や埃が発生します
通常、解体工事現場では、粉塵の飛散を防ぐために「養生シート」と呼ばれるシートで建物の周りを覆いますが、この設置が不十分だったり、シートが古くて破れていたりすると、効果が薄れてしまいます
作業員のマナー
意外に思われるかもしれませんが、現場で作業する作業員の行動やマナーが、近隣トラブルの原因となることも少なくありません
こうしたマナーの問題は、単に個々の作業員の資質だけでなく、その解体業者が従業員教育や現場管理をどの程度重視しているかを反映している場合があります
工事車両の駐車・通行
解体工事には、資材や廃材を運搬するための大型トラックや、重機、作業員の通勤車両など、多くの車両が出入りします
特に住宅密集地など道幅が狭い場所では、大型車両の通行自体がストレスになることもあります。また、公道に足場や養生シートがはみ出す場合や、一時的に車両を停める場合には、警察署への「道路使用許可」の申請が必要になるケースもあります
隣家への損害
細心の注意を払っていても、解体作業中に予期せぬ形で隣接する建物や所有物に損害を与えてしまう可能性はあります
このような物損事故が発生した場合、基本的には施工業者(解体業者)が責任を負い、補修や賠償を行うことになります。そのため、業者が万が一に備えて「損害賠償責任保険」に加入しているかどうかが非常に重要になります
境界線・越境物
隣接する土地との境界線が曖昧な場合や、塀、樹木の枝などが境界線を越えてお互いの敷地に入り込んでいる(越境している)場合に、トラブルが生じることがあります
害虫・害獣
古い建物を解体すると、そこに住み着いていたネズミやゴキブリなどの害虫・害獣が、行き場を求めて近隣の家屋に移動してくることがあります

3. トラブルを未然に防ぐ!解体工事前の準備と対策
これまで見てきたような近隣トラブルは、事前に適切な準備と対策を講じることで、その多くを防いだり、影響を最小限に抑えたりすることが可能です。ここでは、トラブルを未然に防ぐための具体的な方法をご紹介します。
信頼できる解体業者の選定
近隣トラブルを防ぐ上で、最も重要と言っても過言ではないのが、信頼できる解体業者を選ぶことです
- 許可・保険の確認 : まず、その業者が解体工事を行うために必要な建設業許可や解体工事業登録を持っているかを確認しましょう
- 見積もり内容の確認 : 複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。単に総額だけでなく、「一式」と記載されている項目があれば、その内訳を詳しく確認することが大切です
- 業者の姿勢の確認: 見積もり依頼時や打ち合わせ時の担当者の対応、説明の丁寧さなども、その業者の信頼性を判断する材料になります
このような業者選びの段階での確認作業は、単に「良い業者」を見つけるためだけではありません。施主自身が予期せぬトラブルや責任問題に巻き込まれるリスクを回避するための、重要な自己防衛策でもあるのです。
事前の挨拶回り
近隣トラブルを防ぐための最も効果的な対策の一つが、工事開始前の「挨拶回り」です
- なぜ重要か: 事前に挨拶をしておくことで、近隣住民の方々は「いつから、どんな工事が始まるのか」を知ることができ、心の準備ができます
- 誰が、いつ、何を伝えるか: 挨拶回りは、解体業者の担当者だけでなく、可能であれば施主(工事依頼主)も同行することをお勧めします
- 挨拶の範囲: どこまで挨拶に伺うべきか迷うかもしれませんが、一般的には、解体する建物の両隣、真裏、向かい側の家(いわゆる「向こう三軒両隣」)に加え、工事車両の通行などで影響が出そうな範囲のご家庭にも挨拶しておくのが丁寧です。敷地の境界線から10メートル程度の範囲、あるいは建物の高さと同じくらいの水平距離の範囲内の家屋などが目安とされることもあります
現場での対策
工事中のトラブルを物理的に防ぐためには、現場での具体的な対策が不可欠です。信頼できる業者であれば当然実施すべきことですが、施主としてもどのような対策が行われるのかを知っておくと安心です。
- 養生 : 工事現場の周囲に足場を組み、建物を覆うように「養生シート」や「養生パネル」を設置します
- 散水 : 解体作業中に水を撒く(散水する)ことで、粉塵の舞い上がりを大幅に抑えることができます
- 作業時間の遵守 : 事前の挨拶で伝えた作業時間や、法律・条例で定められた作業時間(後述の岐阜市の規制を参照)を厳守することが基本です
- 駐車計画 : 工事車両の駐車場所を事前に計画し、近隣の迷惑にならないように配慮します。敷地内にスペースがあればそこを利用し、なければ近隣のコインパーキングを利用するなど、路上駐車を極力避ける工夫が必要です
- 低騒音型重機の使用 : 可能であれば、比較的新しい低騒音・低振動型の重機を使用することも、近隣への影響を軽減する一助となります
境界線の確認と家屋調査
- 境界確認 : 後々のトラブルを防ぐために、工事開始前に隣接地の所有者と土地の境界線を明確にしておくことが重要です
- 家屋調査 : 特に隣接する建物が近い場合や、振動の影響が懸念される場合には、「家屋調査」を実施することが有効な対策となります

4. もしトラブルが発生してしまったら?冷静な対処法
どれだけ入念に準備や対策を行っていても、予期せぬ事情で近隣から苦情(クレーム)が入ってしまう可能性はゼロではありません。もし、そのような状況になった場合、感情的にならず、冷静かつ誠実に対応することが、問題をこじらせずに解決するための鍵となります。
初期対応:聞く姿勢と謝罪
近隣住民の方が苦情を伝えに来られた場合、まず最も大切なのは、相手の話を冷静に、真摯に聞く姿勢を示すことです
この最初の段階で、言い訳をしたり、反論したりするような態度は禁物です。相手の感情を逆なでし、問題をより大きくしてしまう可能性があります
情報収集と記録
相手の話を聞きながら、苦情の具体的な内容(何が問題なのか、いつ、どこで発生したのかなど)を正確に把握するように努めましょう
そして、苦情を受けた日時、相手のお名前(可能であれば)、苦情の具体的な内容などを、後で参照できるように記録しておくことをお勧めします
解体業者への迅速な連絡
近隣から苦情を受けたら、できるだけ速やかに、その内容を解体業者(現場責任者や担当者)に連絡・相談しましょう
業者選びの段階で、苦情や問い合わせの窓口を業者に一本化し、近隣住民の方にもその旨を伝えておく(挨拶回りの際など)と、施主が直接対応する負担を減らすことができます
具体的な対応策の例
連絡を受けた解体業者は、苦情の内容を調査し、原因に応じて具体的な対策を講じることになります
- 粉塵に関する苦情: 散水(水撒き)の量や回数を増やす
- 騒音に関する苦情: より防音効果の高いシートを追加・交換する
- 振動に関する苦情: 可能であれば、振動が発生しにくい工法に変更する
- 隣家への損害に関する苦情: 業者が状況を確認し、工事による損害であることが明らかになれば、業者が加入している損害賠償責任保険を利用して、補修や賠償を行います
このように、多くの場合、現場作業に関する問題の是正や損害への対応は、解体業者の責任範囲となります
解決が難しい場合
施主、解体業者、近隣住民の間での話し合いで問題が解決しない場合や、悪質な業者とのトラブル、法的な問題が絡むような複雑なケースでは、第三者の専門機関に相談することも検討しましょう。
- 市役所の担当部署 : 騒音・振動・粉塵の発生が著しい、作業時間が守られていないなど、規制や条例に関わる問題については、岐阜市役所の担当部署に相談することができます。特に騒音・振動に関しては**環境保全課(大気・騒音係)**が窓口となります
- 消費生活センター : 解体業者との契約内容に関するトラブルや、サービスの質に関する一般的な苦情については、岐阜市消費生活センターで無料相談を受け付けています
- 弁護士・法テラス : 隣家への損害賠償に関する交渉が難航している、業者との間で契約不履行や高額な追加請求などの金銭トラブルが発生している、といった法的な対応が必要な場合は、弁護士に相談することを検討しましょう
これらの公的な相談窓口や専門家の存在を知っておくことは、万が一、当事者間での解決が困難になった場合の「駆け込み寺」として、大きな安心材料となります。特に、規制違反が疑われる場合や、直接の話し合いがこじれてしまった場合には、客観的な立場からの助言や介入が有効な手段となり得ます
5. 岐阜市での解体工事:知っておきたいルールと相談窓口
解体工事に伴う近隣への影響を最小限に抑えるため、法律や条例によって様々なルールが定められています。岐阜市で解体工事を行う際には、特に「特定建設作業」と呼ばれる、騒音や振動を著しく発生させる可能性のある作業について、市が定める基準や手続きを理解しておくことが役立ちます。これらのルールは主に解体業者が遵守すべきものですが、施主としても知っておくことで、工事が適切に行われているかを確認したり、近隣住民への説明に役立てたりすることができます。
騒音・振動の規制基準
岐阜市では、騒音規制法および振動規制法に基づき、特定建設作業(くい打ち機やブレーカーの使用など、解体工事で一般的に行われる作業が含まれます
- 騒音: 作業現場の敷地境界線上で 85デシベル以下
- 振動: 作業現場の敷地境界線上で 75デシベル以下
これらの数値は、法律で定められた上限値であり、業者はこれを超えないように作業を行う義務があります。参考として、85デシベルは、パチンコ店内や走行中の電車内(80デシベル)よりやや大きい程度の音量とされていますが、静かな住宅街ではかなり大きく感じられる可能性があります
作業時間の制限
特定建設作業を行える時間帯や日数にも、区域ごとに制限が設けられています
岐阜市 特定建設作業の作業時間制限
出典: 岐阜市ウェブサイトの情報
この表が示すように、多くの住宅地が含まれる第1号区域では、作業は午前7時から午後7時までに制限され、1日の作業時間も10時間以内と定められています。また、どちらの区域においても、日曜日や休日の作業は原則として禁止されています
届出義務
解体業者(元請業者)は、特定建設作業を開始する7日前までに、岐阜市役所の環境保全課に必要な事項を届け出る義務があります
相談窓口
岐阜市内で解体工事に関して、近隣トラブルや規制に関する疑問が生じた場合に相談できる主な窓口は以下の通りです。
- 岐阜市役所 環境保全課(大気・騒音係)
- 内容: 工事に伴う騒音、振動、粉塵に関する苦情や相談、作業時間などの規制に関する問い合わせ。
- 電話番号: 058-214-2152
- 場所: 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 岐阜市消費生活センター
- 内容: 解体業者との契約トラブル、サービスに関する一般的な相談。
- 電話番号: 058-214-2666
- 受付時間: 平日 8時45分~17時30分
- 場所: 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所新庁舎2階
- (参考) 岐阜市役所 空家対策課
- 内容: 空き家の解体に関する補助金制度などの相談。
- 電話番号: 058-214-2258
- (参考) 岐阜市役所 建築指導課(耐震係)
- 内容: 建物の安全性や建築基準に関する相談、耐震関連の補助金など。
- 電話番号: 058-265-3904
これらの窓口は、市民が安心して生活できる環境を守るために設置されています。困ったときには、一人で悩まず、これらの公的なサポートを活用することも有効な手段です。
6. まとめ:安心して解体工事を進めるために
岐阜市で解体工事を進めるにあたり、近隣トラブルは多くの方が心配される点ですが、事前の準備と適切な対応によって、そのリスクは大きく減らすことができます。
本記事で解説してきたように、解体工事には騒音・振動・粉塵といった影響が避けられない側面があります。しかし、これらの影響を最小限に抑えるための鍵は、「事前の丁寧なコミュニケーション」と「信頼できる業者選び」、そして**「現場での確実な対策」**にあります。
特に、工事開始前の挨拶回りは、単なる形式ではなく、近隣住民の方々への誠意を示し、理解と協力を得るための最も重要なステップです
また、適切な養生シートの設置や散水による粉塵対策
さらに、岐阜市の騒音・振動・作業時間に関するルール
解体工事は、施主、解体業者、そして近隣住民の方々の三者間の協力と、互いの立場を尊重する「お互いさま」の気持ち
不安な点や疑問点があれば、近隣への配慮を第一に考え、丁寧な説明と確実な施工を心がけている解体工事の専門家に相談することをお勧めします。この記事で得た知識をもとに、皆様が安心して岐阜市での解体工事を進められることを願っています。


 お問い合わせ
お問い合わせ